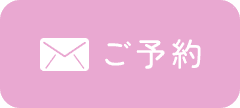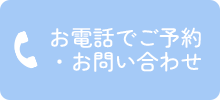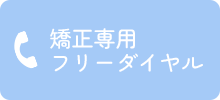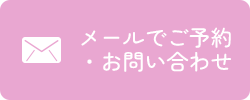ブログ
子どものすきっ歯をそのままにすると!リスクと治療法

こんにちは。福岡県直方市の歯医者・小児歯科・矯正歯科「らいふ歯科クリニック」です。
子どもの歯が生え揃ってくると「前歯の間に隙間がある」といった不安を感じる保護者の方は少なくありません。特に、乳歯から永久歯へと歯並びが変化する時期は見た目の変化も大きく、将来の歯並びや噛み合わせに悪影響が出ないか心配になるでしょう。
すきっ歯は、口腔内の機能や健康にもさまざまな影響を及ぼす可能性がある重要な問題です。「まだ子どもだからそのうち自然に治るのでは?」と様子を見ているうちに、治療のタイミングを逃すケースもあります。
この記事では、子どものすきっ歯の原因から放置するリスク、治療の必要性、具体的な治療法まで詳しく解説します。
すきっ歯とは

すきっ歯とは、歯と歯の間にすき間がある状態を指し、専門的には空隙歯列(くうげきしれつ)と呼びます。特に、前歯にできたすき間を正中離開(せいちゅうりかい)と呼ぶこともあります。
子どもにおいては、乳歯や生え始めたばかりの永久歯にすき間が見られることは珍しくなく、この段階では必ずしも異常とは限りません。特に、乳歯列の時期は、あごの成長に対して歯のサイズが小さいため、自然とすき間ができやすくなります。
このようなすきっ歯は、永久歯が生えそろう過程で自然に解消されるケースも多くあります。
しかし、すきっ歯が大きく、左右のバランスが悪かったり永久歯に生え変わっても改善が見られなかったりする場合は、治療が必要になることもあります。また、すきっ歯は見た目の印象に大きく影響するため、年齢が上がるにつれて本人が気にするようになることもあります。
発音や食べ物の噛みやすさといった機能面にも関係するため、見た目だけの問題だと軽視しないことが大切です。
子どもがすきっ歯になる原因

子どもの歯がすきっ歯になるのには、いくつかの原因があります。ここでは、子どもがすきっ歯になる主な原因をわかりやすく解説します。
乳歯と永久歯の大きさの違い
乳歯は永久歯よりも小さいため、あごの成長に対して歯の幅が足りず、自然とすき間ができやすくなります。特に、乳歯列期にはこのような発育空隙が見られることが一般的で、永久歯が生え揃うまでに自然に埋まるケースも多くあります。
このため、すきっ歯だからといってすぐに心配する必要はありませんが、永久歯が生え揃っても隙間が残る場合には注意が必要です。
上唇小帯の位置異常
上唇小帯とは、上唇の内側と歯ぐきをつないでいる筋のことを指します。これが通常より太かったり前歯の間まで入り込んでいたりすると、歯が中央に寄ることが妨げられ、すきっ歯が残る原因となります。
このタイプのすきっ歯は、治療が必要となるケースが多いです。
指しゃぶりや舌癖などの習慣
指しゃぶりや舌で歯を押す癖(舌突出癖)は、歯並びに悪影響を及ぼすことがあります。これらの癖が長期的に続くと、前歯が押し出されてすき間ができたり噛み合わせが乱れたりする可能性があります。
すきっ歯の原因となるだけではなく、口腔全体のバランスを崩すこともあるため、早期の改善が望ましいです。
遺伝的な要因や顎の成長バランス
歯やあごの形、大きさなどは遺伝の影響を強く受けることが知られています。両親のどちらかがすきっ歯であった場合、子どもにも似た歯並びが現れることがあります。
また、あごの骨の成長が歯の生えるスペースに影響を与えることもあり、骨格的な問題が原因となる場合もあります。
子どものすきっ歯をそのままにするリスク

子どものすきっ歯は成長に伴って自然に治ることもありますが、全てのケースがそうとは限りません。特に、原因が癖や構造的な異常によるものである場合、すきっ歯を放置することにはいくつかのリスクが伴います。
以下では、すきっ歯をそのままにしておくことによって生じる代表的な問題点を解説します。
噛み合わせの乱れによる機能障害が起こる
すきっ歯のまま成長すると、上下の歯の噛み合わせに不調和が生じることがあります。歯がしっかり噛み合わないと、食べ物を十分に噛み砕けなかったり消化に負担がかかったりする可能性があります。
また、特定の歯に過剰な負担がかかると歯の摩耗や顎関節への負担が増し、長期的なトラブルにつながることもあります。
発音や会話に影響を及ぼす
前歯にすき間があると空気が漏れやすくなり、サ行やタ行などの発音に影響を与えることがあります。子どもは言語を学ぶ過程にあるため、発音に支障が出るとコミュニケーションに不安を感じたり、自信をなくしたりすることも考えられます。
見た目のコンプレックスになる
子どもは、成長するにつれて見た目を気にするようになります。すきっ歯が目立つことでからかわれたり、自分の歯並びにコンプレックスを抱いたりするケースも少なくありません。
さらなる歯並びの乱れを引き起こす
すきっ歯を放置すると、他の歯がすき間に向かって傾いたり移動したりすることがあります。その結果、本来の位置に生えるべき永久歯のスペースが足りなくなり、歯並び全体が崩れるリスクもあります。
将来的に矯正治療が複雑化したり、期間や費用が増えたりする可能性もあるため、早期に対応することが重要です。
子どものうちにすきっ歯は治療すべき?

子どものすきっ歯に気づいたとき、保護者の多くが「このまま様子を見ていていいのか、それとも早めに治療すべきなのか」と悩むことでしょう。すきっ歯の治療が必要かどうかは、原因や年齢、歯の生え変わりの進み具合によって異なります。
乳歯列期や混合歯列期(乳歯と永久歯が混在している時期)では、すき間が見られても自然に解消することがよくあります。特に前歯のすき間は、犬歯が生える頃に閉じていくケースが多く、焦って治療を始める必要がない場合も多いです。
上唇小帯の異常や指しゃぶり・舌癖などの習慣が原因であれば、自然治癒が期待しにくいため、早期に対応したほうがよいとされています。癖に関しては、将来の歯並びへの影響を最小限に抑えるためにも、乳歯が抜けて永久歯に生え変わる前に改善することが望ましいです。
矯正治療を始める時期は、子どもの口の状態や成長段階によって異なります。早めに歯科医師に相談することは、最も効果的なタイミングを知る手助けにもなります。
子どものすきっ歯はどうやって治療する?

子どものすきっ歯が自然に治る見込みが少ない場合や原因が明らかなときには、早期に治療を始めることが勧められます。治療方法は原因や年齢、歯の状態によってさまざまであり、必ずしもすぐに矯正器具をつける必要があるとは限りません。
ここでは、子どものすきっ歯に対する代表的な治療方法について解説します。
癖を改善するアプローチ
指しゃぶりや舌癖といった習慣がすきっ歯の原因になっている場合、まずはその癖を取り除くことが治療の第一歩となります。口腔筋機能療法(MFT)と呼ばれるトレーニングもあり、舌の使い方を改善することで歯並びへの悪影響を防げます。
癖を早期に改善することで、矯正が必要なくなる場合もあります。
上唇小帯の処置
上唇小帯の異常がある場合には、小帯切除術という外科的処置が行われることがあります。この処置は局所麻酔で短時間に行われ、出血や痛みも少ないため、小さなお子さまにも対応可能です。
小帯を切除することで前歯が自然に中央へ寄るスペースが確保され、矯正を行う際の負担を軽減できます。
矯正装置による治療
歯並びや噛み合わせに問題がある場合は、矯正装置を用いた本格的な治療が必要になることもあります。小児矯正では、顎の成長を促したりコントロールしたりする装置(拡大床、機能的矯正装置など)を使用することが多いです。
これらは、成長期だからこそ可能な治療方法です。
定期的な観察と経過チェック
すきっ歯の治療では、歯の生え変わりや顎の成長を見ながら適切な時期を見極める経過観察も重要な対応のひとつです。成長段階によって歯並びが自然に変化する可能性があるため、数か月ごとに検診を受けながら、必要な時期に治療へと移行できるよう準備しておきましょう。
まとめ

子どものすきっ歯は、一見すると小さな問題に見えるかもしれませんが、放置することで将来的な噛み合わせの不調やコンプレックスにつながる可能性もあります。特に、指しゃぶりや舌癖、上唇小帯の異常など、明確な原因がある場合には、早めの対応が求められます。
ただし、すべてのすきっ歯が直ちに治療を必要とするわけではなく、成長とともに自然に解消されるケースもあります。そのため、保護者が過度に心配するのではなく、定期的な歯科受診を通じて専門家の判断を仰ぐことが大切です。
子どもの口腔環境は将来の健康にも大きく影響します。お子さまの健やかな成長のためにも、日々の観察と適切なタイミングでの対応を心がけましょう。
お子さまのすきっ歯の治療を検討されている方は、福岡県直方市の歯医者・小児歯科・矯正歯科「らいふ歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。
当院では、虫歯・歯周病の治療だけでなく、歯並びや噛み合わせの治療も行って健康で笑顔あふれる人生[らいふ]を送っていただけるよう努めています。0歳からの虫歯予防や小児の矯正治療なども対応しています。