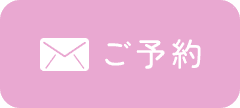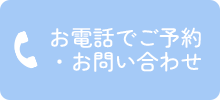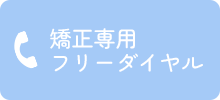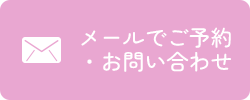ブログ
子どもの反対咬合(受け口)とは?原因・症状・治療法・費用を徹底解説

こんにちは。福岡県直方市の歯医者・小児歯科・矯正歯科「らいふ歯科クリニック」です。
「もしかして反対咬合かも?」とお子さんの歯並びにお悩みの保護者の方も多いのではないでしょうか。反対咬合(受け口)は見た目だけでなく、発音や食事などに影響を及ぼす可能性があるため、早期に治療を受けることが推奨されます。
この記事では、子どもが反対咬合(受け口)になる原因や、そのままにするリスク、治療法、予防法などについて解説します。お子さまの歯並びや噛み合わせが気になるという保護者の方は、ぜひ参考にしてください。
反対咬合(はんたいこうごう)とは

反対咬合(はんたいこうごう)とは、下の前歯が上の前歯より前に出ている状態を指し、受け口とも呼ばれます。
正常な噛み合わせは、上の前歯が下の前歯よりも2〜3mmほど前方に位置している状態ですが、反対咬合の場合はその逆の状態になります。
子どもの場合、骨格が成長する過程で現れることが多く、見た目だけでなく発音や咀嚼にも影響を及ぼすことがあります。乳歯列期や混合歯列期に見られる反対咬合は、成長とともに自然に改善する場合もあります。
しかし、顎の成長バランスに影響を及ぼす可能性があるため、早期の発見と適切な対応が望まれます。
子どもの反対咬合の主な原因

子どもが反対咬合になるのにはさまざまな原因があります。
遺伝的要因
歯の大きさや骨格は遺伝することがあります。そのため、両親のどちらかが反対咬合の場合、子どもも反対咬合になるケースがあるのです。
両親のどちらかが反対咬合の場合は、早めに歯科医師に相談することが望ましいでしょう。
生活習慣や癖による影響
指しゃぶりや舌で歯を押す癖、長期間のおしゃぶり使用など、日常生活の習慣が反対咬合の一因となることもあります。これらの癖が続くと、歯や顎の発育に影響を及ぼし、噛み合わせのバランスが崩れる場合があります。
癖に気づいた際は、無理なくやめられるようサポートし、必要に応じて専門家の指導を受けることが大切です。
骨格の発達異常
生まれつき顎の骨の成長バランスに差がある場合や、成長過程で顎の発達に異常が生じた場合も、反対咬合が起こることがあります。また、外傷や病気などがきっかけで顎の成長に影響が出ることもあります。
骨格の問題が疑われる場合は、専門的な診断と治療が必要となるため、早期の受診が推奨されます。
子どもの反対咬合による症状とリスク

子どもの反対咬合がもたらす主な症状や将来的なリスクについて解説します。
見た目への影響
反対咬合になると、下あごが前に出て見えたり、顔全体のバランスが崩れたりすることがあります。これにより、本人が見た目を気にしたり、心理的な負担を感じたりすることもあるでしょう。
発音や食事への影響
反対咬合の状態では、上下の歯がうまく噛み合わないため、発音が不明瞭になったり、特定の音が出しにくくなったりすることがあります。
また、食べ物を噛み切る・すりつぶすといった動作がしにくくなり、食事に時間がかかったり、しっかり噛めなくなったりする可能性もあります。
将来の歯並びや顎関節への影響
反対咬合を放置すると、成長とともに歯並びや上下のあごの発育バランスに影響が出ることがあります。
これにより、将来的に矯正治療が複雑になることや、顎関節に負担がかかりやすくなるリスクも指摘されています。早期の相談や経過観察が重要とされています。
反対咬合になるのを防ぐ方法

反対咬合になるのを防ぐ方法について解説します。
生活習慣を見直す
お子さまの反対咬合を予防するためには、普段の姿勢や食事の仕方に注意が必要です。
例えば、食事の際はしっかりと両方の奥歯で噛むことを意識しましょう。また、柔らかいものばかりを選ばず、適度な硬さの食材を取り入れることも大切です。
猫背やうつ伏せ寝、頬杖などの習慣も顎の成長に影響を与えることがあるため、日頃から正しい姿勢を心がけましょう。
悪習癖を改善する
指しゃぶりや舌を前に突き出す癖、口呼吸などは反対咬合を引き起こす原因のひとつです。
これらの癖が見られる場合は、まずはお子さま自身にその習慣を自覚してもらい、家族で声かけをしながら少しずつ改善を目指しましょう。無理にやめさせるのではなく、できたことを褒めるなど、前向きなサポートが効果的です。
定期的に歯科医院でチェックを受ける
成長期は顎や歯並びが大きく変化する時期です。定期的に歯科医院でチェックを受けることで、万が一、歯並び・噛み合わせに問題が起こっていても、早期発見・早期対応が可能になります。
また、お子さまの歯並びで気になる変化があれば歯科医師に相談することも重要です。ご家庭での小さな気づきが、将来の健康な歯並びにつながります。
子どもの反対咬合を治療する方法

子どもの反対咬合治療には、ムーシールドなどのマウスピース型の矯正装置や、フェイスマスクなどが用いられます。
ムーシールドは日中1〜2時間程度と就寝時に装着し、舌や口周りの筋肉バランスを整え、顎の成長を誘導する装置です。フェイスマスクは、上顎の成長を促すために顔の外側から力を加える装置です。
永久歯が生えそろってからは、マウスピース矯正やワイヤー矯正で治療を行います。マウスピース矯正は、透明なマウスピースを毎日決められた時間装着して、少しずつ歯並びを整える方法です。
一方でワイヤー矯正は、歯の表面にブラケットと呼ばれる小さな装置を取り付け、そこに通したワイヤーに力を加えることで歯並びを整えます。骨格的な問題がある場合には、外科的な治療が必要になるケースもあるでしょう。
どの矯正方法が適応となるかは、歯並びや顎の状態などによって異なります。そのため、お子さんの歯並びが気になるときは、早い段階で歯科医師に相談することが推奨されます。
治療開始に適した年齢とタイミング
反対咬合の治療は、一般的に6歳頃から始めることが多いですが、歯や顎の成長状態によって適切な開始時期は異なります。早期に治療を開始することで、顎の成長をコントロールしやすくなりますが、必ず歯科医師による診断が必要です。
反対咬合を治療する場合にかかる期間と費用

治療期間には個人差がありますが、1〜3年程度が目安とされています。治療は、初診・診断、装置の装着、定期的な調整、経過観察という流れで進みます。成長や歯並びの変化に合わせて治療内容が変更されることもあります。
反対咬合を治療する場合にかかる費用は、装置の種類や治療内容によって異なります。一般的に自由診療となることが多く、20万〜80万円程度が目安です。詳しくは必ず歯科医院でご確認ください。
早期治療の重要性

反対咬合を治療しないまま成人を迎えると、あごの骨格が不調和な状態が続きます。その結果、見た目に影響が及ぶ場合があるのです。また、矯正治療だけでは改善が難しく、外科的な手術を併用しなければならないケースもあります。
外科的治療は身体的・精神的な負担が大きくなる可能性があるため、成長期のうちに適切な対応を検討することが大切です。
反対咬合の治療法は成長段階によって異なります。早期に歯並び・噛み合わせの異常を発見し、適切な時期に治療を開始することで、骨格的な問題の進行を抑えたり、治療の負担を軽減できたりする可能性があります。
定期的に歯科検診を受け、歯科医師と相談しながら経過を見守ることが重要です。
反対咬合が気になったときの歯科医院・矯正歯科の選び方

反対咬合の治療には、専門的な知識と経験が必要です。小児歯科や矯正歯科のなかでも、子どもの咬合異常に詳しい歯科医師が在籍しているかどうかを確認しましょう。
ホームページや口コミだけでなく、実際に問い合わせて治療実績や診療方針について聞くことも大切です。また、通院しやすい立地や診療時間も考慮し、継続的に通える環境を選ぶことが重要です。
まとめ

反対咬合は、上下の歯の噛み合わせが逆になる状態を指します。子どもが反対咬合になる原因は、遺伝や生活習慣、口周りの癖などさまざまです。
放置すると、見た目に影響を及ぼすだけでなく、発音や食事への影響、将来的な歯並びや顎の成長へのリスクも指摘されています。
治療法は症状や年齢によって異なるため、早い段階で歯科医師に相談することが重要です。
小児矯正を検討されている方は、福岡県直方市の歯医者・小児歯科・矯正歯科「らいふ歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。
当院では、虫歯・歯周病の治療だけでなく、歯並びや噛み合わせの治療も行って健康で笑顔あふれる人生[らいふ]を送っていただけるよう努めています。0歳からの虫歯予防や小児の矯正治療なども対応しています。