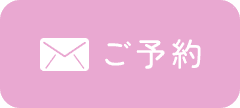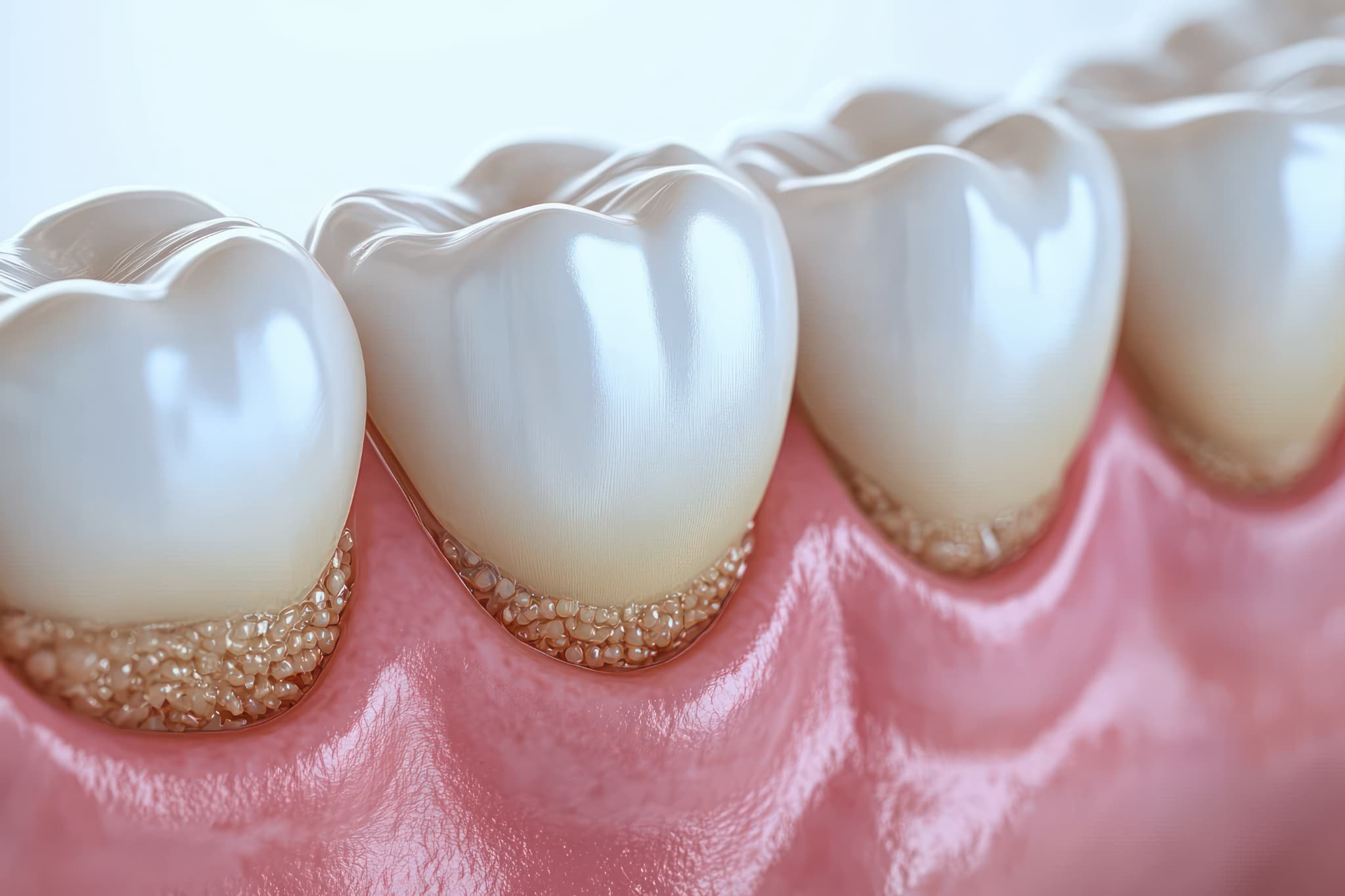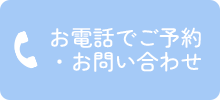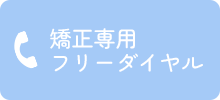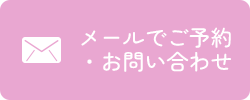こんにちは。福岡県直方市の歯医者・小児歯科・矯正歯科「らいふ歯科クリニック」です。
お子さんの歯並びが気になる保護者の方は多いのではないでしょうか。特に、前歯がなかなか閉じない、口をぽかんと開けていることが多い、発音が不明瞭といったサインがあると、「もしかして歯並びに影響があるのでは?」と不安に思うかもしれません。実はこのような歯並びの問題には、舌の癖が深く関係していることがあります。舌の使い方は無意識のうちに身につくため、気づかないうちに歯や顎の成長に大きな影響を及ぼすことも少なくありません。
今回は、子どもによく見られる舌の癖と歯並びの関係について詳しく解説していきます。
舌の癖とは?
舌の癖とは、舌の使い方に無意識の習慣があることを指します。本来、舌は安静時には上あごの天井(口蓋)に軽く触れ、飲み込むときには前歯に力をかけずに奥へ動くのが正しい位置と動きです。しかし、舌を前に押し出したり、歯の間に挟んだりする習慣がついてしまうと、歯に余計な力がかかり、歯並びや噛み合わせに悪影響を及ぼすことがあります。これがいわゆる「舌癖」です。
子どもに多い舌の癖の種類
前歯が抜けた隙間に舌を入れる
乳歯が抜けて永久歯が生えるまでの間、子どもは抜けた前歯の隙間に舌を入れて遊ぶことがあります。しばらくの遊びであれば問題はありませんが、習慣化すると舌で歯を押す動きが定着してしまい、前歯が噛み合わなくなる「開咬」につながる恐れがあります。
飲み込むときに舌で前歯を押す
嚥下癖とも呼ばれるもので、つばや食べ物を飲み込むときに舌が前に突き出て、前歯を押す癖です。子どもだけでなく大人にも見られることがあります。これが続くと前歯が前方に押し出され、出っ歯(上顎前突)や開咬の原因になります。
舌を上下の歯の間に挟む
無意識のうちに舌を前歯や奥歯の間に置く癖です。歯と歯の間に常に舌があることで、歯が正しく噛み合わず、噛み合わせがずれていきます。
舌癖が歯並びに与える影響
舌は一見やわらかい器官ですが、実際には強い筋肉のかたまりです。日常生活の中で舌を動かす回数は非常に多く、例えば唾を飲み込むだけでも1日に数百回、あるいはそれ以上の回数に及ぶといわれています。そのため、たとえ1回にかかる力が弱くても、舌が歯を押す動作が何度も繰り返されることで、歯は少しずつ動いてしまうのです。歯は顎の骨の中に埋まっていますが、じわじわと加わる圧力には抵抗できず、時間をかけて移動してしまいます。これが、舌癖が歯並びに与える最も大きな影響です。舌癖によって起こりやすい代表的な歯並びの問題は以下のようなものです。
開咬
上下の前歯が噛み合わず、前歯の間に隙間ができる状態です。食べ物を前歯で噛み切ることが難しくなり、発音が不明瞭になることもあります。舌を前に押し出す癖や、長期間の指しゃぶりなどが原因として多く見られます。
出っ歯(上顎前突)
上の前歯が前に傾き、横から見ると前歯だけが突出しているように見えます。見た目の問題だけでなく、転倒したときに前歯をぶつけやすくなる、口が閉じにくいなどのリスクも伴います。舌が前歯を押す力が続くことで、歯が前方に押し出されてしまいます。
発音の不明瞭さ
舌の位置が安定せず、言葉を発する際に正しい舌の使い方ができないと、「さ行」「た行」「な行」などがはっきり発音できなくなることがあります。特にお友達との会話や学校生活で気になることが多くなり、自己表現に影響する場合もあります。
口呼吸の助長
舌癖と口呼吸は相互に悪影響を与えます。舌が前に出て歯を押すと口が閉じにくくなり、自然と口呼吸になりやすくなります。逆に、口呼吸が習慣化すると舌の位置が下がり、正しい場所に舌を置けなくなってしまうのです。これにより歯並びの乱れがさらに進行する悪循環に陥ります。
このように、舌癖は単に歯並びが悪くなるというだけではなく、食べる・話す・呼吸するという日常生活の基本的な動作にまで影響を及ぼす可能性があるのです。
舌癖以外にも注意したい習慣

歯並びに悪影響を及ぼす要因は舌癖だけではありません。無意識に繰り返す日常の小さな習慣も、長期的には歯や顎の成長に大きな変化をもたらします。
鉛筆やお箸を噛む習慣
勉強中や食事中に無意識に鉛筆やお箸を噛んでしまう子どもは少なくありません。硬いものを噛む習慣は特定の歯に強い力をかけ続けるため、歯が移動したり、噛み合わせに不均等な圧力がかかったりして歯並びが乱れる原因となります。また歯の表面が摩耗したり、欠けたりするリスクもあります。
頬杖をつく習慣
勉強中やテレビを見ているときなど、片方の顎に手を当てて頬杖をつく癖も要注意です。頬杖による持続的な圧力は、顎の骨の成長方向にゆがみを生じさせ、顔の非対称や歯並びの不均衡を引き起こす可能性があります。
長時間の指しゃぶり
幼児期には自然な行動として指しゃぶりが見られますが、年齢が上がっても続くと歯並びに悪影響を及ぼします。前歯が前に出たり、開咬になったりするほか、口呼吸や発音への影響も大きくなります。
このような習慣は子どもの生活の中に自然と入り込んでいるため、本人も自覚していないことがほとんどです。親御さんがふとした瞬間に観察し、「あれ、ちょっと気になるな」と思ったときに声をかけることが、将来の歯並びを守る第一歩になります。
まとめ

舌の癖は、子どもにとっては何気ない習慣にすぎません。しかし、その小さな積み重ねが歯並びや噛み合わせに大きな影響を与えることがあります。歯並びを守るためには、舌癖に早く気づき、家庭での工夫や専門医のサポートを取り入れることが大切です。
お子さんのお口の中で気になることがある方は、福岡県直方市の歯医者・小児歯科・矯正歯科「らいふ歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。
当院では、むし歯・歯周病の治療だけでなく、歯並びや噛み合わせの治療も行って健康で笑顔あふれる人生[らいふ]を送っていただけるよう努めています。0歳からのむし歯予防や小児の矯正治療なども対応しています。
当院のホームページはこちら、Web予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。