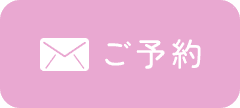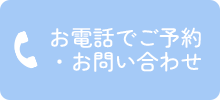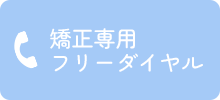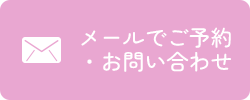ブログ
牛乳をたくさん飲めば歯が強くなるの?歯とカルシウムの関係

こんにちは。福岡県直方市の歯医者・小児歯科・矯正歯科「らいふ歯科クリニック」です。
小児歯科でよくいただく質問のひとつに、「牛乳をたくさん飲めば歯が丈夫になりますか?」というものがあります。牛乳といえばカルシウム、そしてカルシウムといえば「骨や歯を強くする」というイメージが強いですよね。確かにカルシウムは歯の大事な構成成分ですが、実はそれだけでは不十分です。歯の健康を守るには、栄養のバランスや生活習慣も大きく関わってきます。
今回は、カルシウムと歯の関係やカルシウムを多く含む食品、そして効率よく吸収するためのポイントについて詳しく解説します。
カルシウムをたくさんとれば歯が強くなるのか?
歯は外側からエナメル質、象牙質、歯髄の3つの層でできています。このうちエナメル質や象牙質は、カルシウムやリン酸を主成分とする「ハイドロキシアパタイト」という結晶で構成されています。そのため、成長期に十分なカルシウムを摂取することは、しっかりとした歯をつくるうえで欠かせません。
しかし、カルシウムをたくさんとればその分だけ強くなるというわけではありません。人間の体は、一度に吸収できるカルシウムの量が限られています。特に、乳歯や永久歯の形成は成長段階に合わせて進んでいくため、必要以上のカルシウムをとっても余分は体外に排出されてしまいます。
さらに、歯の硬さはカルシウムの量だけで決まるものではありません。歯を守る唾液の働き、歯磨きによるプラーク除去、砂糖の摂取量の管理などもむし歯予防には大切です。つまり、カルシウムは歯を作る材料として重要ですが、完成した歯を守るためには日常のケアや食生活のバランスが必要なのです。
カルシウムを多く含む食品
牛乳はカルシウムが豊富で吸収率も高い食品ですが、それだけがカルシウム源ではありません。乳製品が苦手な子でも、ほかの食品からカルシウムをとることは十分可能です。
乳製品
乳製品はカルシウムの含有量が高く、また乳糖やカゼインがカルシウムの吸収を助けてくれるため効率よく摂取できます。
● 牛乳
● ヨーグルト
● チーズ
魚介類
魚の骨にはカルシウムがぎっしり詰まっています。小魚や桜えびなど丸ごと食べられる食品は、特におすすめです。
● ししゃも(骨ごと食べられる魚)
● いわしの丸干し
● 桜えび
● 煮干し
大豆製品
大豆製品はカルシウムだけでなく、たんぱく質やイソフラボンも豊富で、成長期の体作りに役立ちます。
● 豆腐
● 納豆
● 厚揚げ
● おから
野菜類・海藻類
野菜や海藻にもカルシウムは含まれますが、乳製品や魚に比べると吸収率は低めです。そのため、ほかの食品と組み合わせて摂るのがポイントです。
● 小松菜
● モロヘイヤ
● ひじき
● わかめ
カルシウムの吸収を良くするには?

カルシウムは歯や骨を作る重要な栄養素ですが、ただたくさん摂ればよいというわけではありません。せっかく食事や飲み物から摂取しても、体に吸収されず排出されてしまえば意味がないのです。カルシウムの吸収率は、食品の種類や一緒に摂る栄養素、生活習慣によって大きく変わります。ここでは、カルシウムを効率よく体に取り込むためのポイントをご紹介します。
ビタミンDを一緒にとる
ビタミンDは、腸でカルシウムの吸収を助ける栄養素です。十分なビタミンDがなければ、どれだけカルシウムを摂っても吸収効率が低下してしまいます。ビタミンDは、鮭、サンマ、イワシなどの脂の多い魚や、しいたけ、きくらげといったきのこ類に多く含まれています。食事での摂取に加え、日光を浴びることでも体内で合成されます。特に春から秋にかけては、1日15〜30分ほどの外遊びや散歩が理想的です。冬場や日照時間の少ない地域では、意識してビタミンDを含む食品を増やすとよいでしょう。
適度な運動
カルシウムは吸収されるだけでなく、骨や歯にしっかり定着することが重要です。その定着を促すのが、運動による骨への刺激です。特にジャンプや走る動きが多い運動は、骨密度を高める効果が高いとされています。縄跳び、鬼ごっこ、ボール遊び、体操など、遊びの中で自然に取り入れると続けやすくなります。また、外での運動は日光浴にもつながり、ビタミンDの合成を助けるという相乗効果もあります。
リンやカフェインの過剰摂取を避ける
カルシウムの吸収を阻害する成分にも注意が必要です。代表的なものがリンとカフェインです。リンは体に必要なミネラルですが、加工食品やインスタント食品、清涼飲料水などに含まれるリン酸塩を大量に摂ると、カルシウムと結合して吸収を妨げます。カフェインにはカルシウムの排出を促す作用があり、コーヒーや紅茶だけでなく、子どもが好むチョコレートやコーラにも含まれています。完全に避ける必要はありませんが、日常的に多く摂らないよう心がけましょう。
バランスの良い食事
カルシウムだけで歯や骨が作られるわけではありません。土台となるたんぱく質、カルシウムの骨への沈着を助けるビタミンK、カルシウムの代謝に関わるマグネシウムなど、さまざまな栄養素が必要です。肉、魚、卵、大豆製品、野菜、海藻などをバランスよく組み合わせ、特定の食品に偏らないようにしましょう。例えば、小松菜と厚揚げの煮びたし、鮭のムニエルとほうれん草のソテー、ヨーグルトに果物とナッツを加えるなど、1食の中で複数の栄養素を同時に摂れる工夫がおすすめです。
牛乳を飲むときのポイント
少量を分けて摂る
一度にたくさん飲むよりも、1日数回に分けて摂ったほうが吸収率が上がります。
食事と一緒に
食事中に摂取すると、ほかの栄養素との相乗効果で吸収が良くなります。
無理に大量摂取しない
牛乳を飲みすぎると、食事のバランスが崩れたり、お腹をこわす原因になることもあります。
まとめ

牛乳をたくさん飲むことは、カルシウム補給において確かに有効です。しかし、カルシウムの摂取量が歯の強さのすべてに繋がるわけではありません。歯を丈夫に保つには、カルシウムだけでなく、ビタミンDやたんぱく質など他の栄養素、そして日々の歯磨きや生活習慣が欠かせません。カルシウムを多く含む食品は牛乳や乳製品だけでなく、小魚、大豆製品、野菜や海藻にもあります。これらをバランスよく取り入れ、吸収を助ける栄養素や習慣も意識しましょう。
お子さんのお口の中で気になることがある方は、福岡県直方市の歯医者・小児歯科・矯正歯科「らいふ歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。
当院では、むし歯・歯周病の治療だけでなく、歯並びや噛み合わせの治療も行って健康で笑顔あふれる人生[らいふ]を送っていただけるよう努めています。0歳からのむし歯予防や小児の矯正治療なども対応しています。
当院のホームページはこちら、Web予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。