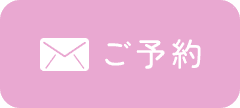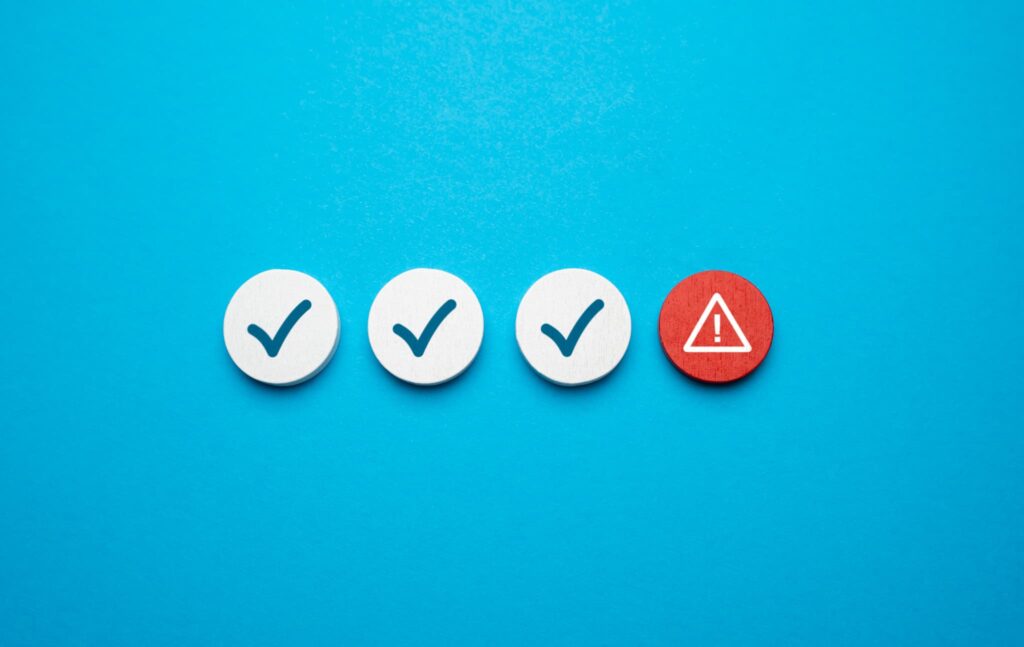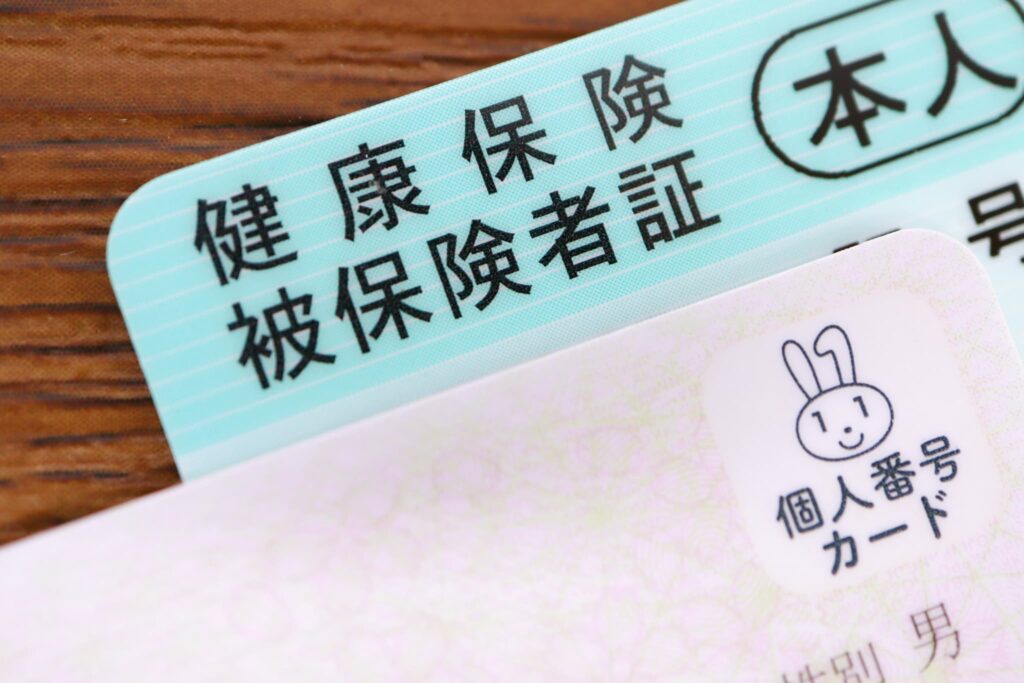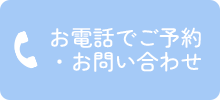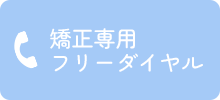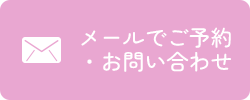こんにちは。福岡県直方市の歯医者・小児歯科・矯正歯科「らいふ歯科クリニック」です。
お子さまの歯並びや噛み合わせについては、多くの保護者の方が気がかりにしている事項かもしれまさん。不正咬合(ふせいこうごう)とは、上下の歯が正しく噛み合わない状態を指します。正常な噛み合わせは食事や発音、さらには顎の発育にも大きな影響を与えますが、不正咬合があるとこれらの機能がうまく働かず、健康や生活にさまざまな影響を及ぼすことがあります。特に成長段階にある子どもの不正咬合は、早期に気づいて対応することが重要です。本記事では、不正咬合の種類と子どもに見られやすい不正咬合の特徴、治療について詳しく解説します。
不正咬合とは?
不正咬合は、歯が正常な位置に生えないことで、上下の歯の噛み合わせが乱れている状態です。歯並びが悪いと口の中の清掃も十分に行き届かずにむし歯や歯周病のリスクが高まるだけでなく、見た目や顎の成長にも悪影響を与えることがあります。不正咬合は遺伝的要因によって引き起こされることもありますが、指しゃぶりや舌癖といった悪習慣も原因となります。
不正咬合があることのデメリット
不正咬合は、口腔内だけでなく全身にさまざまな悪影響を及ぼすことがあります。まず、食事面でのデメリットが挙げられます。噛み合わせが悪いと食べ物を十分に咀嚼できず、消化不良を引き起こす可能性があります。さらに発音にも影響を与え、特定の音がうまく発声できないことがあります。
次に、歯の健康面においても問題があります。不正咬合があると歯ブラシが届きにくい部分ができ、むし歯や歯周病のリスクが高まります。また、顎に過度の負担がかかるため、顎関節症を引き起こすこともあります。特に、顎の痛みや口の開閉が困難になる症状は日常生活に大きな支障を与えます。
そして、見た目や心理的な影響も無視できません。不正咬合は顔のバランスに影響を与え、笑顔に自信が持てなくなることがあります。これにより対人関係や自己肯定感に悪影響を及ぼすことがあり、特に成長期の子どもにとっては重要な問題です。
このように不正咬合は健康面や生活面で多くのデメリットを伴うため、早期に適切な対応を行うことが大切です。
不正咬合の種類
不正咬合はさまざまな種類に分類され、それぞれ異なる治療が必要です。代表的な不正咬合についてご紹介します。
上顎前突(じょうがくぜんとつ)
上顎前突は、上の前歯が下の前歯よりも大きく前に出ている状態です。一般的に「出っ歯」として知られており、見た目だけでなく食べ物を噛み切りにくい、発音がしにくいなどの問題を引き起こします。遺伝的な要因や長期間の指しゃぶり、舌を前に押し出す癖が原因となることがあります。
下顎前突(かがくぜんとつ)
下顎前突は下の前歯が上の前歯よりも前に出ている状態で、いわゆる「受け口」と呼ばれるものです。食べ物が噛みづらいだけでなく下顎に過剰な負担がかかり、顎関節症のリスクが高まります。骨格性の要因が多く成長に伴って悪化する可能性があるため、早期に治療することが重要です。
開咬(かいこう)
開咬は上下の前歯が噛み合わず、前歯の間に隙間ができてしまう状態です。この状態では食べ物を前歯で噛み切ることが難しくなり、発音にも支障をきたします。長期間の指しゃぶりや舌の突き出し癖が原因となることが多い傾向にあります。
叢生(そうせい)
叢生は歯が重なり合って生え、歯並びが乱れた状態です。歯が重なり合っている部分の清掃が難しくなるため、むし歯や歯周病のリスクが高まります。歯が生えるスペースが不足していることが主な原因です。
交叉咬合(こうさこうごう)
交叉咬合は、上下の歯の噛み合わせがずれて片側または両側で歯が交差している状態です。左右の顎の成長に不均衡を生じさせ、顔が左右非対称になることがあります。
過蓋咬合(かがいこうごう)
過蓋咬合は、上の前歯が下の前歯を過剰に覆ってしまう状態です。この状態が続くと下の歯や顎に過度な負担がかかり、顎関節症や歯の摩耗を引き起こすことがあります。
子どもに多い不正咬合の原因
子どもの不正咬合は、遺伝的要因以外にも生活習慣や環境的な要因が大きく影響します。
指しゃぶりや舌癖
長期間の指しゃぶりや舌癖は上顎や下顎の成長に影響を与え、不正咬合の原因となります。特に3歳以降になっても指しゃぶりが続く場合、上顎前突や開咬を引き起こすリスクが高まります。舌癖も舌を前に突き出すことで歯列に影響を与えるため、早めに癖を改善することが重要です。
乳歯の早期喪失
乳歯は永久歯が正しい位置に生えるためのガイド役を果たしていますが、むし歯や外傷などで早期に失われると永久歯の生えるスペースが不足し、叢生やその他の不正咬合を引き起こすことがあります。乳歯を健康に保つことが、将来の正しい噛み合わせを維持する上で非常に重要です。
不適切な食習慣
柔らかい食べ物ばかりを食べると顎の発達が不十分になり、歯が正しい位置に生えにくくなることがあります。適度な硬さの食べ物を噛むことが顎の正常な成長を促すため、バランスの取れた食事が大切です。
遺伝的要因
不正咬合には遺伝的な要因も大きく関わっています。親が不正咬合の場合子どもも同様の問題を抱える可能性が高いため、歯科検診で経過を観察する必要があります。
子どもに対する不正咬合の治療法
子どもの不正咬合は、早期に発見し適切な治療を行うことで将来的なリスクを軽減できます。ある程度成長するまでは様子をみることもありますが、不正咬合そのものが自然に治癒することは基本的にはありません。したがって、歯列矯正で専門的な治療を受ける必要があります。子どもの矯正治療では、不正咬合の程度やタイプに合わせた装置が使用されます。取り外し可能なマウスピース型の装置から固定式の装置までさまざまな選択肢があるため、どの方法が適しているかは矯正専門の歯科医師とよく相談して決めましょう。
子どもの不正咬合を防ぐためのポイント

子どもの不正咬合を防ぐためには、以下のポイントに気をつけることが重要です。
定期的な歯科検診
早期に問題を発見するために、定期的な歯科検診を受けることが重要です。特に永久歯が生え始める時期には、噛み合わせの状態をしっかり確認してもらいましょう。
生活習慣の見直し
指しゃぶりや舌癖など歯列に悪影響を与える習慣がないかを確認し、早めに改善することが大切です。
バランスの取れた食事
噛む力を鍛えるためにも、柔らかい食べ物ばかりではなく適度に硬いものも食べるように意識しましょう。
まとめ
不正咬合は子どもの成長や生活にさまざまな影響を与える可能性があるため、早期の発見と適切な対応が重要です。定期的な歯科検診や正しい生活習慣を通じて不正咬合を防ぎ、必要に応じて適切な治療を受けるよう心がけましょう。