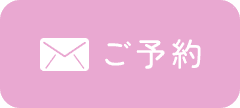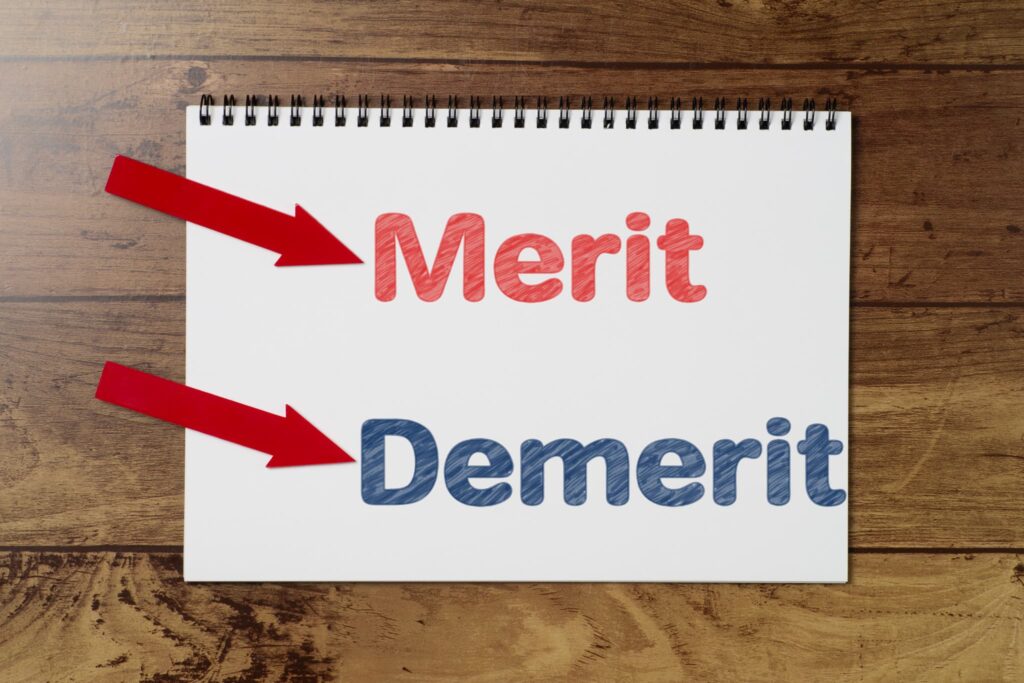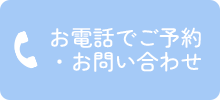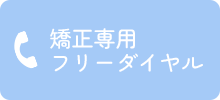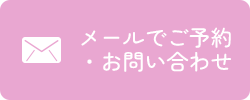こんにちは。福岡県直方市の歯医者・小児歯科・矯正歯科「らいふ歯科クリニック」です。
嚙み合わせに違和感があり、治療を検討している方もいるでしょう。「噛み合わせの治療ってどんなことをするの?」「期間や費用はどれくらい?」と、悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
この記事では、噛み合わせ治療にかかる期間や費用についてまとめました。併せて、噛み合わせの悪い状態を放っておくリスクや、治療を受けるメリット・デメリットについても詳しく解説します。
嚙み合わせ治療の期間とは

噛み合わせ治療にかかる期間は、症例や治療法により異なります。矯正治療の場合は1~3年程度、被せ物・ブリッジ・部分入れ歯の場合は1~2か月程度でしょう。
ただし、根管治療が必要な場合や治療範囲が広い場合は、治療期間が長引く可能性があります。インプラントの場合は、6か月~1年程度、外科矯正の場合はトータルで3~5年程度必要です。
嚙み合わせが悪いまま放っておくとどうなる?

噛み合わせが悪い状態で放置すると、様々なトラブルの原因となります。以下では、主なトラブルについて詳しく解説します。
顎関節症を発症する
噛み合わせが悪い状態で放置していると、顎の関節に負担がかかり顎関節症を発症するリスクがあります。顎関節症を発症すると、口を大きく開けた時にカクッと音がしたり、口の開け閉めが難しくなったりします。
症状が進行すると痛みが強くなり、痛みにより口を開けられなくなることもあるでしょう。
肩こりや頭痛を引き起こす
口周りの筋肉は首や肩にもつながっているため、噛み合わせが悪いと顎の筋肉だけでなく連動している首や肩の筋肉も硬くなり血流も悪化します。その結果、首や肩の凝り、頭痛を引き起こす可能性があります。
腰痛や痺れ、全身の疲労感などの症状も悪い噛み合わせが原因だったケースもあります。長引く不調がある場合は、噛み合わせの問題がないか歯科医院でチェックしてもらいましょう。
むし歯や歯周病
噛み合わせが悪い場合は、歯並びも悪いケースがほとんどです。歯並びが悪いと、歯の重なり合う部分の歯磨きが難しく、汚れが残ってむし歯のリスクが高まります。
また、特定の歯に負荷がかかっているため、歯周病を進行させるケースがあります。
顔の歪み
顎関節の痛みから、片側の歯だけで噛む癖がつくと一部の筋肉ばかりが発達します。年数が経過すると、左右差が出て顔のバランスが崩れることもあります。見た目に対するコンプレックスにつながることもあるようです。
嚙み合わせ治療を受けるメリットについて

以下では、嚙み合わせ治療で得られるメリットをまとめました。
むし歯・歯周病・口臭のリスクを軽減
噛み合わせを治療すると、清掃性が向上して磨き残しが少なくなります。また、細菌の繁殖も抑えられることから、むし歯や歯周病、口臭のリスクが軽減されます。
消化器官の負担が軽減する
上下の歯が正しい位置で噛めるようになると、食べ物を効率よく咀嚼できるようになります。胃や腸などの消化器官の負担を軽減でき、栄養の吸収に良い影響をもたらします。
Eラインを作れる
噛み合わせが悪いと、美しい横顔の基準となるEラインが崩れることがあります。治療により噛み合わせが改善されれば、Eラインが整う可能性があります。
嚙み合わせ治療を受けるデメリットについて

矯正治療や補綴治療での嚙み合わせ治療にはデメリットはほとんどありませんが、外科矯正治療を行う場合は、いくつかのデメリットがあります。
入院する必要がある
手術の種類や病院により異なりますが、受け口の手術は術後の回復や様子を見るために約1~2週間の入院が必要です。この期間、仕事や学校を休まなければならないため、計画的に手術を受ける必要があります。
痛みや腫れが起こる
口の中を切開するため、術後は傷が治癒する過程で痛みや腫れを伴います。痛みや腫れの度合いには個人差がありますが、手術後1週間程度は特に痛みを感じやすいです。
術後の痛みは、痛み止めで対処できるケースがほとんどです。
痺れや感覚麻痺が起こる可能性がある
術後、稀に唇や顎の痺れや感覚の鈍化などが起こる可能性があります。この症状は短期間であれば1か月、長くて1年程度続くことがあります。
術後に気になる症状がある場合は、我慢せずに歯科医師に相談しましょう。
費用が高額になる
手術の費用は、歯科医院によって異なる場合があります。保険が適用される場合の治療費は50~70万円程度、保険が適用されない場合は150~400万円程度が相場です。
なお、指定された医療機関を受診し、額変形症と診断された場合のみ保険が適用されます。手術後のマウスピース矯正や裏側矯正には保険が適用されない可能性があるため、事前に確認しておきましょう。
嚙み合わせ治療の費用はどのくらいかかる?
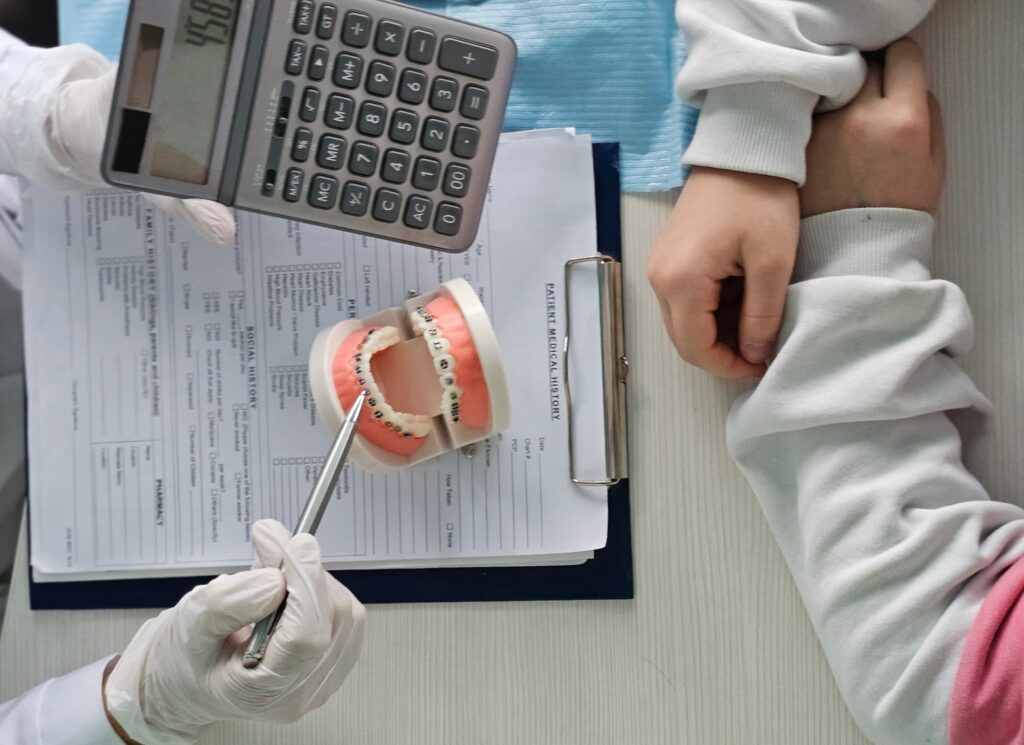
噛み合わせ治療にかかる費用は、治療法により異なります。以下では、治療法別に費用の目安について解説します。
歯科矯正
歯科矯正は、選択する矯正装置の種類により費用が異なります。
例えば、ワイヤー矯正の費用は、60〜170万円が目安です。ワイヤー矯正の中でも、歯の表側に矯正装置を装着する表側矯正は60~130万円程度、裏側に装着する裏側矯正では、100~170万円程度が目安です。
マウスピース矯正の場合は、60~100万円程度が目安です。どの方法で治療するのかは、歯科医院で詳しい検査を受けた後で歯科医師と相談しながら決めましょう。口内の状態によっては、希望する治療法を選べない可能性があることは留意してください。
また、矯正治療には基本的に保険が適用されません。自由診療となるため、費用は歯科医院により異なります。詳しい費用については、事前に歯科医院で確認しましょう。
補綴(ほてつ)治療
補綴治療は、被せ物などを装着して噛み合わせをはじめとした歯の機能を回復させます。ブリッジや部分入れ歯、インプラントなども含まれ、それぞれ価格が異なります。
保険が適用される場合(3割負担)の費用の目安は、以下のとおりです。
- 被せ物:1本4,000円程度
- ブリッジ:2~3万円程度
- 部分入れ歯:5,000円~2万円程度
自由診療の場合の費用の目安は、以下のとおりです。
- 被せ物:1本10~15万円程度
- ブリッジ:5~30万円程度
- 部分入れ歯:15~30万円程度
- インプラントは:1本30~50万円
被せ物で費用を抑えたい場合は、保険が適用される銀歯などを選択するとよいでしょう。審美性を重視して、セラミックなどを選択すると費用が高額になります。
また、補綴治療に用いられる補綴物は、数年~数十年ごとに交換しなければなりません。交換にかかる費用についてもしっかり把握しておきましょう。
外科矯正治療の費用
矯正治療だけでは治療が難しい場合、外科治療が行われます。その際は、矯正にかかる費用に外科手術の費用が加算されます。
3割負担のケースでは、手術と矯正治療で30~90万円程度が目安です。自由診療の場合は200万円以上かかることもあります。症例によって費用や保険適用の可否が異なるため、噛み合わせでお悩みの方は、まず歯科医院へ相談してみましょう。
まとめ

完全に整った噛み合わせの人はほとんどいません。噛み合わせに多少の問題がある方がほとんどです。また、噛み合わせが悪い場合、治療せず自然に治ることはなく、放置していると頭痛や肩こり、顎関節症などの不具合が悪化します。
年齢を重ねるにつれ、歯が移動したりすり減ったりして噛み合わせも変化します。些細な噛み合わせの変化が、むし歯や歯周病はもちろん、新たなトラブルの原因になることもあるでしょう。そのため、定期的なチェックが必要です。
噛み合わせの治療を検討する方は多くありませんが、噛み合わせを治療すると、見た目が改善できるだけでなく、全身の健康にも良い影響を与えます。少しでも噛み合わせに違和感を覚えたら、早めに歯科医院で噛み合わせをチェックしてもらいましょう。
噛み合わせの治療を検討されている方は、福岡県直方市の歯医者・小児歯科・矯正歯科「らいふ歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。
当院では、虫歯・歯周病の治療だけでなく、歯並びや噛み合わせの治療も行って健康で笑顔あふれる人生[らいふ]を送っていただけるよう努めています。0歳からの虫歯予防や小児の矯正治療なども対応しています。