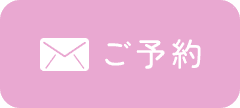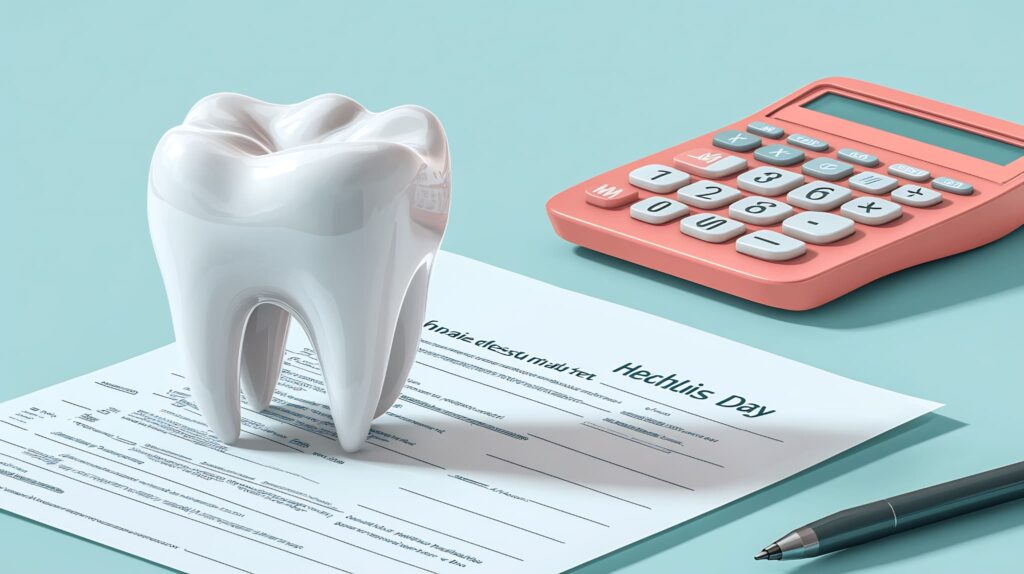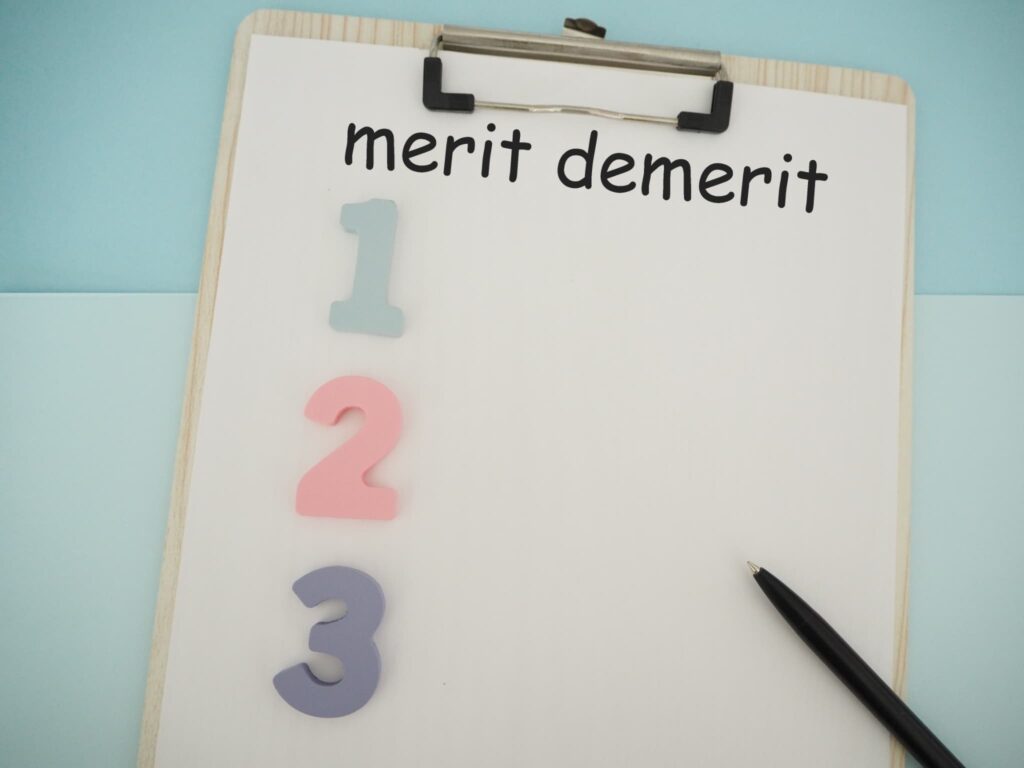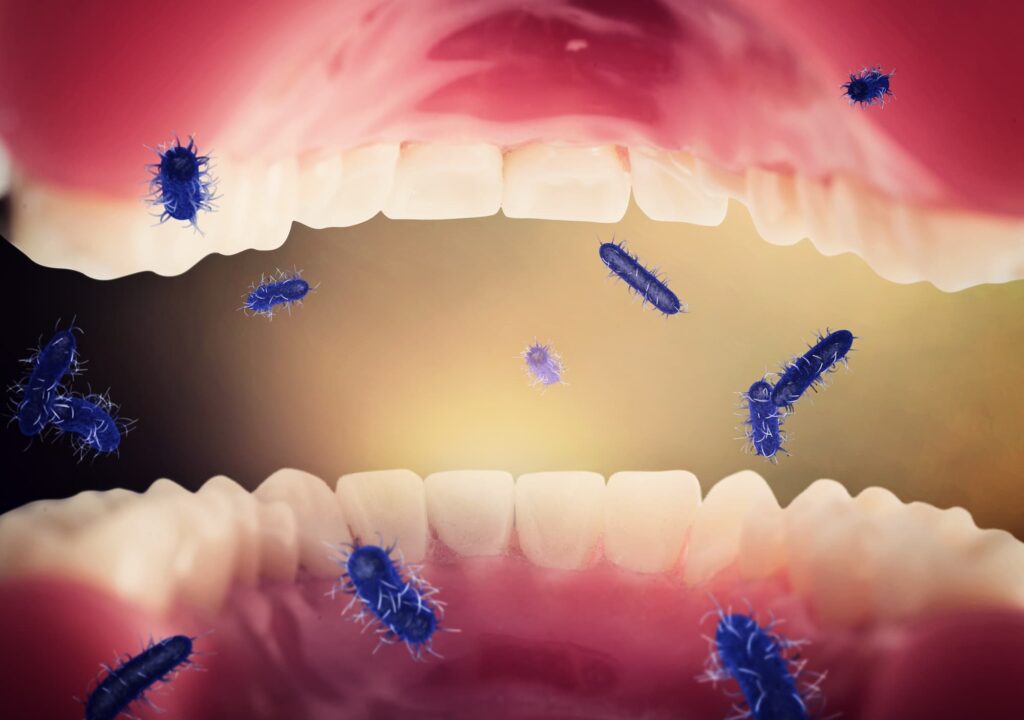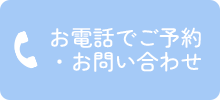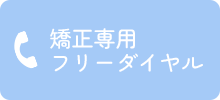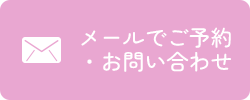こんにちは。福岡県直方市の歯医者・小児歯科・矯正歯科「らいふ歯科クリニック」です。
インビザライン・ファーストは、子どものためのマウスピース矯正方法です。歯列矯正にはさまざまな方法がありますが、インビザライン・ファーストでは透明なマウスピースを使用するため、目立ちにくくお子さまの負担を軽減してあげられます。
しかし、治療にかかる費用に不安を覚えている方も多いのではないでしょうか。
今回は、インビザライン・ファーストの費用について詳しく解説します。費用の負担を抑える方法もご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
インビザライン・ファーストとは

インビザライン・ファーストは、マウスピースを使用して子どもの歯並びを矯正する方法です。乳歯と永久歯が混在する6歳~10歳頃のお子さまが対象です。
インビザライン・ファーストでは顎の成長を利用しながら歯列を矯正していきます。歯の移動のみを行う大人向けのインビザライン矯正とは、治療の目的が異なります。
インビザライン・ファーストの特徴は、顎の成長を促しながら歯の位置を調整できることです。他の小児矯正では、顎の拡大と歯並びの調整は同時に行えません。永久歯が綺麗に生え揃うためのスペースを作りながら歯を移動させるため、治療の負担を軽減できるのです。
また、インビザライン・ファーストでは着脱できるマウスピースを使用します。自由に食事できる点や、矯正治療中も歯磨きなどのケアが行いやすい点など、メリットの多い治療法です。
ただし、マウスピースの装着時間を守ることや、破損しないように保管することなど、自己管理が重要です。
インビザライン・ファーストの費用

インビザライン・ファーストの費用相場は、40万~80万円です。基本的には自由診療になるので、費用は歯科医院ごとに異なります。治療全体にかかる費用を一括で支払うトータルフィー制度を取り入れている歯科医院もありますが、工程ごとに支払いが発生することもあります。
費用の内訳
インビザライン・ファーストの費用の内訳は、以下の通りです。
カウンセリング費用
矯正治療を開始する前に、まずは歯科医師に口腔内の状態を確認してもらいます。インビザライン・ファーストで治療可能かどうか確認し、治療方針について相談します。
カウンセリングは無料で行っている歯科医院もありますが、5,000円~1万円ほど費用がかかる場合もあります。この段階で、矯正治療に関する疑問や不安について相談しておきましょう。
検査費用
矯正治療をすることが決まれば、精密検査を行います。検査内容は歯科医院によって異なりますが、レントゲン撮影などの画像検査が中心です。画像検査で顎の骨の状態や歯の位置を把握し、治療計画を立てていきます。
費用相場は、1万~5万円程度です。
マウスピース作成費
矯正治療の費用の大半を占めるのが、マウスピースの制作費です。費用相場は、40万~60万円ほどでしょう。
精密検査の結果を基に、オーダーメイドのマウスピースを作成します。
インビザライン・ファーストは成長期の子どもを対象とした治療なので、成長過程でマウスピースが合わなくなって再制作が必要になることもあります。この場合は追加費用がかからないケースが多いですが、事前に確認しておくことを推奨します。
通院費
矯正治療中は、治療の進行具合や歯の状態を確かめるために、定期的に通院しなければなりません。通院にかかる費用は、1回あたり3,000~5,000円程度の医院が多いです。
通院を怠れば計画通りに治療が進まず、矯正期間が延びてしまう可能性があります。医師の指示に従って通院しましょう。
保定期間の費用
矯正治療が終わったあとは、歯が後戻りしないようにリテーナーと呼ばれる保定装置を装着する保定期間があります。保定装置の費用は、2万~5万円が相場です。
また、保定期間中も、口腔内の状態を確認するために定期的な通院が必要です。通院ごとに診察料として3,000~5,000円ほどかかるのが一般的です。
インビザライン・ファーストで追加費用が必要となるケース

インビザライン・ファーストの費用相場を紹介しましたが、場合によっては追加費用が必要になるケースがあります。追加費用が発生するような主なケースは、以下の通りです。
マウスピースの破損・紛失
マウスピースの破損や紛失があった場合、マウスピースの再制作が必要になります。マウスピースの再制作には、追加費用が必要なことが多いです。
マウスピースを作り直すには時間もかかるため、治療期間も延びてしまいます。マウスピースの破損や紛失が起こらないように、正しい取り扱い方や保管方法についてお子さまへ指導するようにしましょう。
口腔内トラブルが起こったとき
矯正治療をしている途中で虫歯や歯周病などの口腔内トラブルが起これば、矯正を中断して治療を優先します。治療が中断されれば治療期間が延びるので通院回数が多くなり、費用が追加で必要になります。
また、治療を中断することで歯の後戻りが起これば、マウスピースの再制作が必要になります。この場合も、追加費用が発生するでしょう。
治療期間が延びた場合
インビザライン・ファーストでは、マウスピースを1日20時間以上装着しなければなりません。また、定期的に新しいマウスピースに交換しながら歯を移動させていきます。
装着時間が短い場合や、指示通りにマウスピースを交換しなかった場合、マウスピースが合わなくなって作り直しが必要になる可能性があります。治療期間がのびて通院回数も増えてしまうため、費用が多くかかります。
インビザライン・ファーストは保険適用の対象?

インビザライン・ファーストを含め、矯正治療は基本的に保険適用外になります。保険は、病気や機能的な問題を回復・改善することが目的の最低限の治療に適用されます。矯正治療は審美性や機能性の向上のために行われることが多く、必要最低限の治療とは認められないのです。
ただし、先天的な異常によって引き起こされている不正咬合や、日常生活に支障をきたすほど重度の噛み合わせの悪さなどの場合は、保険が適用される可能性があります。ご自身で判断するのは困難なので、歯科医師に相談してみましょう。
インビザライン・ファーストの費用負担を抑える方法

インビザライン・ファーストの費用は高額になることが多いため、費用負担を少しでも軽減したいと考える方も多いのではないでしょうか。インビザライン・ファーストの費用負担を抑える方法は、以下のとおりです。
医療費控除を活用する
1年間に支払った治療費が一定額を超える場合、医療費控除を受けられる可能性があります。医療費控除は、確定申告の際に申告をすることで、税金の一部が還付される制度です。矯正治療の費用が安くなるわけではなりませんが、経済的負担を軽減できます。
通院の際に利用した公共交通機関の費用も対象で、ご家族の治療費もあわせて申請することが可能です。
ただし、審美性の改善のための治療は医療費控除の対象になりません。
治療期間を延ばさない
インビザライン・ファーストでは、最初に治療計画が立てられます。計画通りに治療が進めば追加費用が発生しないため、計画時に予定した費用で治療を終えられるでしょう。
マウスピースの破損や紛失が起こったり、適切にマウスピースを装着していなかったり、治療期間が延びれば治療費が追加で発生する可能性が高いです。マウスピースを適切に管理し、虫歯にならないように日々のケアをしっかり行いましょう。
デンタルローンを利用する
デンタルローンは、歯科治療専用のローンです。一般的なローンよりも金利が低いことが多いです。一括払いが難しい場合には、デンタルローンを利用して支払いを分割にすることも方法の一つです。
ただし、デンタルローンに対応していない歯科医院もあるので、事前に確認しておきましょう。また、デンタルローンを利用するには、審査を通過する必要があります。月々の負担を減らせますが、手数料や金利で総額が増えることも理解しておきましょう。
まとめ

インビザライン・ファーストの費用相場は、40~80万円ほどです。口腔内の状態や歯科医院によって費用が変動するので、事前に確認しておきましょう。
インビザライン・ファーストの治療費を増やさないためには、治療が長引かないように正しくマウスピースを装着して管理することが大切です。医療費控除やデジタルローンの利用によって費用の負担を軽減できることもあるため、歯科医院にご確認ください。
インビザライン・ファーストを検討されている方は、福岡県直方市の歯医者・小児歯科・矯正歯科「らいふ歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。
当院では、虫歯・歯周病の治療だけでなく、歯並びや噛み合わせの治療も行って健康で笑顔あふれる人生[らいふ]を送っていただけるよう努めています。0歳からの虫歯予防や小児の矯正治療なども対応しています。