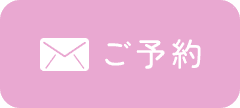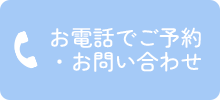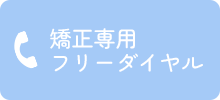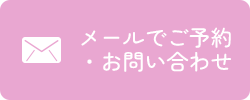ブログ
指しゃぶりは何歳まで様子を見ても大丈夫?成長と歯並びへの影響を解説

こんにちは。福岡県直方市の歯医者・小児歯科・矯正歯科「らいふ歯科クリニック」です。
赤ちゃんや乳児の指しゃぶりは自然な行動の一つであり、多くの保護者の方が経験する悩みです。乳児期には安心感を得るために指しゃぶりをすることが一般的ですが、年齢が上がるにつれてやめる子も増えていきます。しかしなかなかやめられない場合、「このまま続けても大丈夫なのか?」「歯並びに悪影響はないのか?」と心配になることも多いでしょう。
今回は、指しゃぶりの発達的な意味、何歳まで様子を見てよいのか、歯並びへの影響、やめさせる方法について詳しく解説します。
指しゃぶりの発達的な役割
指しゃぶりは新生児期から始まり、乳児期を通じてよく見られる行動です。特に生後2〜3か月頃から吸啜反射が強くなり、手や指を口に入れることが増えます。指しゃぶりは赤ちゃんにとって自己安定の手段であり、眠るときや不安なときにすることが多い傾向にあります。また、感覚の発達にも役立ち、口の中の感覚を通じて世界を探索する行動です。
一般的に2〜3歳頃になると指しゃぶりの頻度は減り、遊びや会話に夢中になることで自然と卒業していく子が多いです。しかし、4歳を過ぎても頻繁に指しゃぶりを続ける場合は、歯並びや発音に影響を及ぼす可能性が出てきます。
何歳まで様子を見てもよいのか?
指しゃぶりが自然な成長過程の一部であることは確かですが、年齢が進むにつれて注意が必要になります。
3歳頃まで
この時期の指しゃぶりは、特に問題視する必要はありません。ほとんどの子どもは、自然に頻度が減っていきます。無理にやめさせるよりも、安心できる環境を提供しながら成長を見守ることが大切です。
4〜5歳頃
4歳を過ぎても指しゃぶりが続く場合、口腔や歯並びへの影響が少しずつ現れる可能性があります。特に、前歯のかみ合わせに影響を与えたり、出っ歯の原因になったりすることがあります。この時期には、子どもと話し合いながら徐々に指しゃぶりを減らす工夫をするとよいでしょう。
指しゃぶりが歯並びに及ぼす影響

指しゃぶりは、乳幼児期には自然な行動のひとつですが、長期間続くと歯並びや噛み合わせに影響を及ぼすことがあります。特に、3歳を過ぎても習慣が続いている場合は注意が必要です。歯や顎の成長に影響を与え、将来的に矯正治療が必要になることもあります。以下のような歯並びの問題が発生しやすくなります。
開咬
開咬とは、上下の前歯がしっかりと噛み合わず、隙間ができてしまう状態のことです。指しゃぶりを続けることで指が前歯を押し広げる力が加わり、歯が正常な位置からずれてしまうのです。この状態になると食べ物を前歯で噛み切ることが難しくなったり、発音に影響が出たりすることがあります。特に「サ行」や「タ行」の発音が不明瞭になりやすく、言葉の発達にも影響を及ぼす可能性があります。
上顎前突
いわゆる「出っ歯」と呼ばれる状態で、上の前歯が通常よりも前に傾いてしまう噛み合わせの異常です。指しゃぶりを長期間続けることで指が上の前歯を前方に押し出し、結果的に歯が前に突き出るようになってしまいます。その影響で口が自然に閉じにくくなり、常に口が開いた状態になりがちです。これにより口呼吸の習慣がついてしまい、口腔内が乾燥しやすくなり、虫歯や歯肉炎のリスクが高まることもあります。
叢生
指しゃぶりは、歯の位置だけでなく、顎の成長にも影響を与える可能性があります。顎の成長が適切に行われないと歯が本来の位置に収まりきらず、歯並びが乱れてしまうことがあります。特に前歯だけでなく奥歯の噛み合わせにも影響を及ぼすことがあり、噛み合わせのバランスが崩れると、食事の際に十分に噛むことができなくなったり、顎関節に負担がかかったりすることもあります。そのため、将来的に矯正治療が必要になるケースも少なくありません。
指しゃぶりをやめさせる方法
指しゃぶりをやめさせるには、無理にやめさせようとするのではなく、子どもの気持ちを尊重しながら自然に卒業できるようにサポートすることが大切です。指しゃぶりは安心感を得るための行動であるため、単に「やめなさい」と叱るだけでは逆効果になってしまうこともあります。以下の方法を試しながら、子どもがストレスを感じずに指しゃぶりを卒業できるようにしましょう。
ポジティブな声かけをする
指しゃぶりを否定するのではなく、「もうすぐお兄さん・お姉さんだね」と励ましたり、「手を使って遊ぶのが楽しいね」と別の行動に意識を向けることが有効です。また、「指しゃぶりをしない時間が増えたね!すごいね!」と成功したことを褒めることで、子どもの自信につながります。無理にやめさせるのではなく、「できたこと」を積み重ねることで、自然と指しゃぶりの頻度が減っていくでしょう。
寝る前のリラックス方法を工夫する
指しゃぶりは眠る前に多く見られるため、寝る前の習慣を変えることで改善しやすくなります。例えば、絵本の読み聞かせをすることで、指しゃぶりの代わりに別の安心できる習慣を作ることができます。また、お気に入りのぬいぐるみを抱かせることで、指を口に入れる代わりに手を使って安心感を得られるようになります。
歯科医師に相談する
指しゃぶりが長く続き歯並びに影響が出始めている場合は、歯科医に相談することをおすすめします。歯科医院では指しゃぶりによる歯並びへの影響を診断し、必要に応じてマウスピース型の装置を提案することがあります。例えば、夜間だけ使用する装置をつけることで、指しゃぶりの習慣を抑えることができます。また、歯科医師から子どもに直接「このままだと歯並びが悪くなるよ」と説明してもらうことで、子ども自身がやめようと意識するきっかけになることもあります。
まとめ

指しゃぶりは乳児期には自然な行動ですが、4歳以降になっても続く場合は歯並びや噛み合わせに影響を及ぼす可能性があるため、徐々にやめる工夫をしていくことが大切です。子どもにプレッシャーを与えず、ポジティブな方法でサポートしながら、健康な歯並びを育てていきましょう。
お子さまのお口の中で気になることがある方は、福岡県直方市の歯医者・小児歯科・矯正歯科「らいふ歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。当院ではむし歯や歯周病の治療だけでなく、歯並びや噛み合わせの治療も行って健康で笑顔あふれる人生[らいふ]を送っていただけるよう努めています。0歳からのむし歯予防や小児の矯正治療なども対応しています。
当院のホームページはこちら、Web予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。