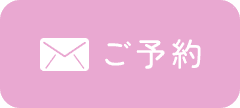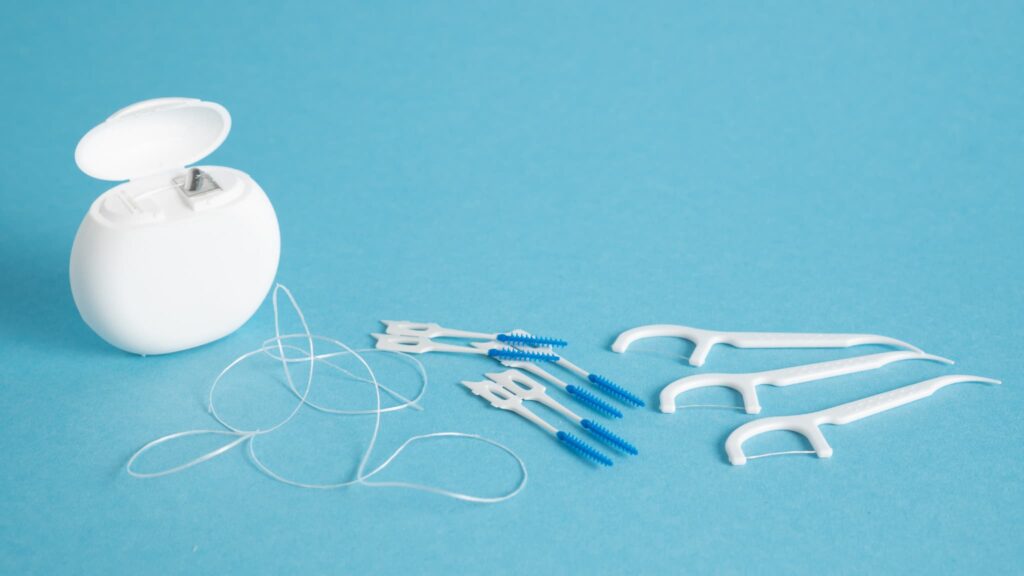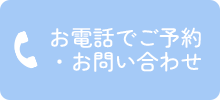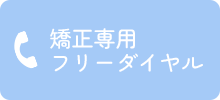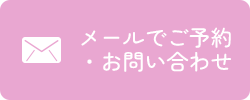こんにちは。福岡県直方市の歯医者・小児歯科・矯正歯科「らいふ歯科クリニック」です。
子どもの歯の健康を守るためには、年齢に応じた適切な歯ブラシを選ぶことが重要です。成長に伴い口腔内の環境や歯磨きの習慣も変化していくため、適した歯ブラシを使用することでむし歯予防や歯の健康維持につながります。今回は、年齢別の歯ブラシ選びのポイントや注意点について詳しく解説します。
歯の生え始め~1歳ごろの歯ブラシ選び
赤ちゃんの歯は生後6ヶ月ごろから下の前歯(乳中切歯:下の中央の乳歯)が生え始め、その後、上の前歯、奥歯と順に生えていきます。この時期の赤ちゃんの口の中はとても敏感で、まだ歯磨きに慣れていないため、無理にブラシを使って磨こうとすると、嫌がってしまうことがあります。そのため、最初は歯ブラシではなく、ガーゼやシリコン製の歯ブラシを使用し、歯や歯ぐきを優しく拭うことから始めるのが一般的です。
歯ブラシ選びのポイント
シリコン製の歯ブラシ
シリコン製の歯ブラシは、柔らかい素材でできており、赤ちゃんの歯ぐきを傷つけにくいのが特徴です。ブラシ部分がシリコンでできているため、歯が生え始めたばかりの赤ちゃんでも安心して使用できます。歯磨きというよりは、歯ぐきをマッサージするように使うことで、赤ちゃんが歯ブラシに慣れるための第一歩として取り入れやすくなります。特に、乳歯が生えることで歯ぐきがムズムズして不快感を覚える赤ちゃんにとっては、シリコン製の歯ブラシを噛むことで、不快感が和らぐ場合もあります。
ガーゼや歯磨きシート
まだ歯が数本しか生えていないうちは、ガーゼや歯磨きシートを使うのも効果的です。指に巻いたガーゼや、市販の歯磨きシートを使って、赤ちゃんの歯や歯ぐきを優しく拭き取ることで、口の中を清潔に保つことができます。
赤ちゃんが持ちやすい設計
この時期の赤ちゃんは、ものをつかんで口に入れることが大好きな時期でもあります。そのため、歯ブラシを選ぶときは、赤ちゃん自身が持ちやすいデザインのものを選ぶとよいでしょう。例えば、持ち手が太くて握りやすいものや、滑りにくい素材でできているものがおすすめです。また、誤って喉の奥に入ってしまうのを防ぐために、ストッパーが付いているものを選ぶのも安全対策の一つです。最近では、赤ちゃんが自分で噛んで遊びながら歯磨きの練習ができるリング型の歯ブラシも人気です。
幼児期(1歳6ヶ月から3歳ごろ)の歯ブラシ選び
1歳6ヶ月から3歳にかけて、子どもの乳歯は徐々に生えそろい始めます。この時期には上下の前歯が計12本生え、さらに奥歯も4本生えてくるため、口の中の環境が大きく変化します。乳歯は永久歯に比べてエナメル質が薄く、むし歯になりやすいため、適切な歯磨き習慣を身につけることが非常に重要です。特に、奥歯が生え始める2歳ごろからはむし歯のリスクが高まるため、早い段階でしっかりとケアを始めることが求められます。
歯ブラシ選びのポイント
幼児期の歯磨きを効果的に行うためには、適切な歯ブラシを選ぶことが大切です。子どもに合った歯ブラシを使用することで、歯磨きを嫌がらず、スムーズに習慣化することができます。歯ブラシを選ぶときは、以下のポイントを押さえておきましょう。
ヘッドが小さめのものを選ぶ
幼児の口は小さく、乳歯もまだ小さいため、大人用の歯ブラシでは磨きにくく、細かい部分まで届かないことがあります。そのため、ヘッドが小さい歯ブラシを選ぶことで、奥歯までしっかりと磨くことができ、汚れを効果的に落とすことができます。前歯や奥歯の生え際はむし歯になりやすいため、細かい部分まで磨きやすい歯ブラシを選びましょう。
毛先が柔らかいものを選ぶ
幼児の歯ぐきは非常にデリケートで、大人用の硬い歯ブラシを使用すると傷つけてしまう可能性があります。毛先が柔らかいものを選ぶことで、歯ぐきを傷つけることなく、優しく磨くことができます。
持ち手が太くて握りやすいものを選ぶ
1歳6ヶ月から3歳ごろになると、子どもは少しずつ自分で歯ブラシを持って磨こうとするようになります。この時期は、まだ手の力が弱く、細かい動きが苦手なため、持ち手が太くて握りやすい歯ブラシを選ぶことが大切です。太めの持ち手は、子どもが自分で握りやすく、無理なく歯磨きをすることができるため、歯磨き習慣を楽しく身につける手助けになります。
歯磨き習慣を楽しく身につける工夫

適切な歯ブラシを選ぶだけでなく、子どもが楽しく歯磨きを続けられる工夫も大切です。例えば、キャラクターがデザインされた歯ブラシを選ぶことで、子どもの興味を引きやすくなります。また、歯磨きの時間に歌を歌ったり、アニメーション動画を見せたりすることで、歯磨きの時間を楽しめるようにするのも効果的です。
学童期(小学生ごろ)の歯ブラシ選び
学童期(小学生ごろ)は、乳歯が抜けて永久歯が生えそろう大切な時期です。一般的に6歳ごろから12歳ごろまでの間に乳歯が抜け、最終的に28本の永久歯へと生え変わります。この期間は「混合歯列期」と呼ばれ、乳歯と永久歯が混在することで歯並びが一時的にデコボコになり、歯磨きが難しくなります。そのため、磨き残しが発生しやすく、むし歯になるリスクが高まります。
特に、第一大臼歯(6歳臼歯)は生え始めの段階では高さが低く、周囲の歯よりも少し下がった位置にあることが多いため、歯ブラシが届きにくいのが特徴です。また、歯の溝が深く、細かいため、食べかすやプラークが溜まりやすく、むし歯になりやすい部分でもあります。
この時期の子どもたちは、自分で歯を磨く習慣を身につける一方で、まだ完璧に磨くことができません。保護者の仕上げ磨きが重要になりますが、それと同時に、適切な歯ブラシを選ぶことも非常に大切です。
歯ブラシ選びのポイント
第一大臼歯は、口の奥に生えてくるため、磨き残しが発生しやすい部位です。そのため、奥までしっかり届くような形状の歯ブラシを選ぶことが大切です。柄の部分が長すぎると子どもが扱いにくくなり、短すぎると奥まで届かなくなるため、適度な長さのものを選びましょう。また、ヘッド部分が少し細長く設計されているものや、先端がやや細くなっている歯ブラシは奥歯まで届きやすく、しっかりと磨くことができます。
まとめ

子どもの年齢や歯の成長に合わせた歯ブラシを選ぶことは、むし歯予防や健康な歯を育てるためにとても重要です。歯磨きは単なる習慣ではなく、一生の口腔環境を左右する大切なケアのひとつです。お子さんが自分で楽しく歯磨きできるよう、適切な歯ブラシを選び、親子で一緒に歯磨きの習慣を育んでいきましょう。
お子さまのお口の中で気になることがある方は、福岡県直方市の歯医者・小児歯科・矯正歯科「らいふ歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。当院ではむし歯や歯周病の治療だけでなく、歯並びや噛み合わせの治療も行って健康で笑顔あふれる人生[らいふ]を送っていただけるよう努めています。0歳からのむし歯予防や小児の矯正治療なども対応しています。
当院のホームページはこちら、Web予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。